どうも、ノマドクリエイターのショウヘイ( @shohei_creator )です。


ブログアシスタントのふーちゃんです。
小説の書き方には、いくつかの体裁があります。その代表例は、『●人称▲視点』という形で表現される人称と視点です。
視点は、一人称視点と三人称視点の2種類に分けられます。三人称視点は、単視点と多視点と神視点の3種類に大別されます。
小説の書き方は、どの人称視点を使うかによって、様変わりします。書きたい作風に合わせて、適切な人称視点を選ぶことが大切です。
今回の記事では、小説の人称視点の詳細と使い分けについて解説します。
小説の人称と視点とは
まずは、「小説の人称と視点とは何か』という根底から、正しく理解しましょう。
小説における人称とは、「語り部は誰か?」を意味します。
一人称は『登場人物』が語り部であり、三人称は『物語に登場しない第三者』が語り部です。
![]()

小説における視点とは、「どのように見聞きしているか?」を意味します。
一人称視点であれば、『語り部の登場人物の五感』を使っています。そのため、小説で描写できる範囲は、語り部の五感で得られる情報に制限されます。
三人称視点であれば、特定の人物の背後に付き従って見聞きする場合(単視点)、飛行ドローンのように各所を飛び回って見聞きする場合(多視点)、天から全てを見通す神として見聞きする場合(神視点)に分けられます。
![]()

小説の人称視点の概要・特徴・使い分け


これから、一人称視点と三人称視点について、個別に詳しく説明していきます。


その前に、人称視点の概要・特徴・使い分けについて、簡単に紹介しておきますね。
先に枠組みを知っておくと、人称視点についての理解が深まりやすくなりますよ。
- 概要
- 物語の語り部は、主人公。物語で描写できることは、主人公の五感を通して得られる情報に限られる。
- 特徴
- 主人公の心理をそのまま描写できるので、主人公の人物設定を深堀りできることが強み。その反面、他人の心理を直接 描けないので、他の登場人物を深堀りしづらい。
- 適している物語描写
- 主人公の性格に癖が強いと、機知に富んだ会話やツッコミを展開できる。コメディ系の物語を書きたい時に向いている。
【単視点(背後霊視点)】
- 概要
- 特定の登場人物(主人公)に的を絞り、物語を描写していく。
- 特徴
- あくまでも第3者の目線で物語を描くが、主人公と心がつながっているので、主人公の心理だけは直接 描ける。たとえるなら、主人公と心が繋がっている背後霊の視点。
- 適している物語描写
- 特定の人物を中心に物語を展開しつつも、一人称視点よりも視野の広い描写を書きたい場合に適している。
【多元視点(飛行ドローン型)】
- 概要
- 単視点と異なり、さまざまな登場人物を通して、物語を描写できる。
- 特徴
- 視点移動が出来る反面、単視点のように、登場人物の心理を直接 描けない。たとえるなら、空中を自在に飛んで回る飛行ドローンの視点。
- 適している物語描写
- 活躍を描きたい登場人物が複数(2~3人)いる場合に適している。
【神視点】
- 概要
- 物語で起きる あらゆることを知り尽くしている神様の視点。
- 得意・不得意
- 自由に視点移動できるし、登場人物の心理も そのまま描写可能。現在だけでなく、過去や未来の出来事も描写できる。その反面、登場人物の設定を深堀りすることは難しい。
- 適している物語描写
- 戦記や群像劇のように、多くの登場人物の活躍を万遍なく描きたい場合に適している。
小説の一人称視点とは|メリット・デメリットについて
小説の一人称視点は、語り部の目線で物語が展開されます。大半の場合は、主人公が語り部を務めます。
小説の地の文は、「私は~~」や「俺は~~」というように、一人称の文章表現になります。
語り部を通して小説を書き進めるので、物語を描写できる範囲は、語り部の五感で得られる情報に限られます。
![]()

また、語り部以外の登場人物の思考と感情は、語り部の推測として表現されます。読心能力でもないかぎりは、他人の心を読み取れないからです。
![]()

小説の一人称視点の強みは、語り部の思考や感情をそのまま描写できることです。
語り部が癖の強い人物なら、独特な感覚で世界を解釈します。当然ながら、語り部の世界観も独特です。語り部の思考や感情にも、面白味が生まれます。
語り部がノリの良い人物なら、他の登場人物とテンポのいい会話劇が始まります。語り部が心の中で思っているツッコミを地の文に書けるので、まるで漫才のようなコントを展開できるでしょう。
![]()

小説の一人称視点の強みを活かすなら、少しひねくれた語り部を使ったコメディ要素の強い物語が適しています。
一人称視点の具体例は、化物語です。
化物語の語り部(主人公)である阿良々木暦は、物語の始まりでは、世の中に対して皮肉めいた態度を取っています。友だちがいないことについて指摘された時に、「友達は作らない、人間強度が下がるから」と返事したことは、阿良々木暦の初期の人物像を表す名言です。
物語が進むほどに、阿良々木暦が機知に富んだツッコミを入れる人物であることが判明してきます。他の登場人物と繰り広げる会話劇は、多くの読者の腹筋を崩壊させたことでしょう。
巻を追うごとに、阿良々木暦の異常性(変態性)が増していくので、彼の思考と感情が描かれている地の文は、それだけで読み物として面白くなりました。
化物語の章の1つ【ひたぎクラブ】から、いくつか具体例となる会話を掲載しておきます。
戦場ヶ原「それにしてもお尻が痛いわ。じんじんする。スカートに皺がよっちゃったし」
阿良々木「僕の責任じゃない」
戦場ヶ原「言い逃れはやめなさい。切り落とすわよ」
阿良々木「どの部位をですかっ!?」戦場ヶ原「唾を飛ばさないでくれる?童貞がうつるわ」
阿良々木「女に童貞がうつるか!」
戦場ヶ原「唾を飛ばさないで。素人童貞がうつるわ」
阿良々木「認めましょう、僕は童貞野郎です!」阿良々木「言葉の暴力って知ってるか」
戦場ヶ原「なら言葉の警察を呼びなさいよ」戦場ヶ原「こいつ呼ばわりもやめて」
阿良々木「じゃあ、なんて呼べばいいんだよ」
戦場ヶ原「戦場ヶ原様」
阿良々木「…………」
地の文:この女、正気か。
阿良々木「……センジョーガハラサマ」
戦場ヶ原「片仮名の発言はいただけないわ。ちゃんと言いなさい」
阿良々木「戦場ヶ原ちゃん」
地の文:目を突かれた。
阿良々木「失明するだろうが!」
戦場ヶ原「失言するからよ」
阿良々木「何だその等価交換は!?」
戦場ヶ原「銅四十グラム、亜鉛二十五グラム、ニッケル十五グラム、照れ隠し五グラムに悪意九十七キロで、私の暴言は錬成されているわ」
阿良々木「ほとんど悪意じゃねーかよ!」
戦場ヶ原「照れ隠しというのは嘘よ」
阿良々木「一番抜けちゃいけないところが抜けちゃった!」出典元:化物語|ひたぎクラブ
小説の一人称視点でやってしまいがちな失敗
小説の一人称視点で書く時に、やってしまいがちな失敗として、主人公の五感を超えた情報まで描写してしまうことが挙げられます。
小説の一人称視点は、語り部の五感を通して、物語を描写します。したがって、語り部が感じられない情報を描写できません。
しかし、小説を書く作家自身は、物語については何でも知っています。そのため、ついつい語り部の五感を超えた情報も書いてしまいがちです。
放課後。僕が部室に入ると、友人の佐藤が机に突っ伏していた。
「どうした、調子が悪いのか?」
「ああ、ちょっと腹の調子がな……」
佐藤は腹を擦りながら、苦しそうに呻いた。彼は昼食に牛乳を飲みすぎたので、腹を下しているのだ。 ← 語り部が知り得ない情報
「腹の調子か。保健室で胃薬をもらって来たらどうだ」
「……あ、そっか。保健室に行けば、胃薬が手に入るな。ちょっと保健室に行って来る」
佐藤はグッと親指を立ててみせると、のろのろとした動きで部室から出て行った。
小説の三人称視点とは
小説の三人称視点は、物語に登場しない第三者が語り部になります。そのため、客観的な描写が可能です。
たとえ天変地異が起きようとも、冷静に現在の状況を描写できます。
![]()
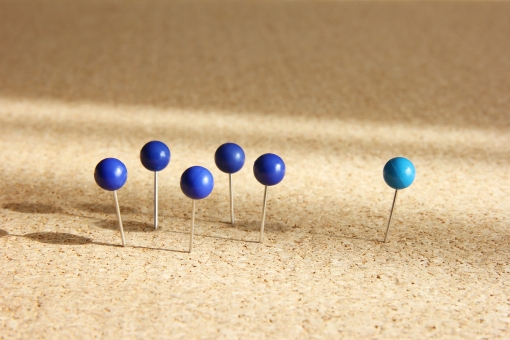
小説の三人称視点は、『どれくらい視点移動するか』や『どこまで情報を開示するか』によって、次の3種類に分けられます。
- 三人称単視点(背後霊視型)
- 三人称多元視点(飛行ドローン型)
- 三人称神視点(全知全能型)
小説の三人称単視点(背後霊型)とは|メリット・デメリットについて
小説の三人称単視点とは、特定の登場人物の後ろを追うようにして、物語の展開を描写する方法です。
たとえば、主人公に追従するとしましょう。この場合は、主人公を中心とする場面展開を詳しく描写できます。
ただし、一人称視点とは違って、描写できる範囲を主人公の五感に制限されません。主人公が見逃した・聞き逃した情報であっても、第三者の視点から描写できます。
![]()

三人称視点の中でも、単視点の強みは、追従する登場人物の内面を描写できることです。
追従する登場人物と心が繋がっている第三者なので、登場人物がどんなことを考えたのか・どんな気持ちを抱いたのかについても、詳しく描写できます。
三人称単視点は、たとえるなら、背後霊のような感じです。登場人物と魂の一部が同化しているので、その人物の思考・感情を読み取れるわけです。
![]()
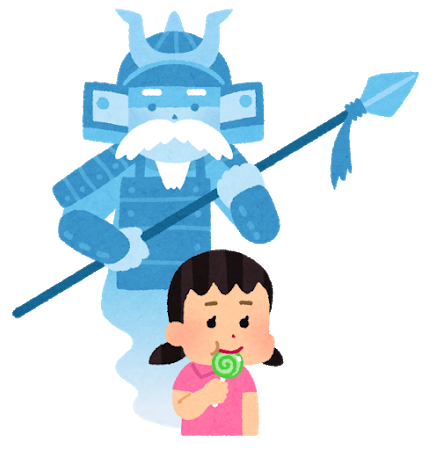


主人公を中心にして物語を描きたいが、主人公の五感や価値観に描写を縛られたくない。
そんな場合は、三人称単視点を使いましょう。


なお、三人称単視点は、追従する登場人物の内面のみを描写できます。他の登場人物については、内面を描写できません。
同じ場面で複数の登場人物の内面を書けるとしたら、それは三人称神視点に分類されます。注意してくださいね。
小説の三人称多視点(飛行ドローン型)とは|メリット・デメリット
小説の三人称多視点とは、複数の主要な登場人物に的を絞り、テレビチャンネルを切り替えるように視点を変える方法です。
![]()

三人称多視点も、第三者の視点から物語の展開を描写できます。三人称単視点との違いは、特定の人物に縛られずに、自由に視点移動できることです。
たとえるなら、飛行ドローンです。ドローンの下部には、ビデオカメラが装着されています。違う登場人物の様子を映したかったら、その場所までブーンと飛んで行けます。
![]()

三人称多視点の欠点は、登場人物の内面を描写できないことです。
三人称単視点のように、登場人物に憑依しているわけではありません。あくまでも、ドローンに装着されたビデオカメラのように、その場の状況を映像として描写するのみです。「●●は、~~と思った」というような内面描写は出来ません。
![]()



三人称多視点は、視点移動は出来る反面、登場人物の心理を描写できません。
『客観的な描写を重視しつつ、時には特定の登場人物の内面も描写したい』という場合は、三人称単視点を活用してください。


三人称多視点の強みを活かすなら、『数多くの登場人物がどんな風に活躍するのか』に重点が置かれる戦記や群像劇に適しています。
![]()

小説の三人称神視点(全知全能型)とは|メリットとデメリット
小説の三人称神視点は、あらゆることを知っている神様の視点です。
どこで何が起きているかは把握していますし、登場人物が何を考えているのかもお見通しです。
![]()



三人称神視点は、三人称単視点・多視点のいいとこ取りです。自由に視点移動できるだけでなく、登場人物の内面も描けます。
また、現在に起きていることだけでなく、過去や未来の出来事ですらも描写できます。目に見えない存在すらも「ここに透明な●●が存在している」と描写できます。
全知全能ですから、なんでも知っています。


三人称神視点に欠点があるとすれば、超越者の視点であるが故に、臨場感が無くなることですね。
さながら、テロップ解説付きのテレビ映像を眺めている気分になります。
![]()

小説の一人称視点&三人称視点のタブー


小説で人称視点を使う時は、いくつかのタブーがあります。
1つ1つ説明していきますね。
タブー1:視点移動のやりすぎ
小説の人称視点は、視点移動のやりすぎに注意してください。
一人称視点にしろ三人称視点にしろ、なんの前触れもなく視点移動されると、読者は「あれ、今は誰の視点なんだ?」と混乱してしまいます。
たとえるなら、とあるテレビ番組を視聴中に、別の番組を切り替えられるような状態です。読者は急に場面が変わって戸惑いますし、まだ見ていたい場面を切り替えられたことにイラつきます。
![]()



もしも視点を切り変えたかったら、章の切り替わり時におこなってください。
章が切り替わる時は、必然的に場面も大きく変わります。自然な形で視点移動が可能です。


ただし、一人称視点については、視点移動を必要最小限にした方がいいですよ。
一人称視点は、人生を体験する感覚に近い味わいがあります。現実のように、特定の人物(自分)だけの視点から物語が綴られていた方が、読者にとって馴染みやすいです。
タブー2:異なる人称視点を混ぜる


異なる人称視点を混ぜるとは、1つの物語(1つの巻)の中で、一人称視点と三人称視点を繰り返すことです。
一人称視点と三人称視点は、混ぜるべきではありません。最初に一人称視点で書き始めたら、最後まで一人称視点で書いてください。三人称視点にしても同様です。


たとえ章の変わり目に視点を変更したとしても、一人称視点と三人称視点が混じっていると、読者さんは「あれ、なんか描写の仕方がいきなり変わったな」と混乱してしまいます。
タブー3:多くの登場人物を通した一人称視点は使う


小説の一人称視点を使う時は、なるべく主人公だけを語り部にして、物語を展開させましょう。
複数人の一人称視点が使いたかったとして、主人公を含めて、多くとも3人までです。


多くの登場人物で一人称視点を使おうとすると、読者は「今は誰の一人称視点なんだ?」と戸惑います。読者にとってストレス源になるわけです。
また、一人称視点の強みは、特定の人物の設定を深堀りできることです。多くの登場人物で一人称視点を使ってしまったら、人物設定を深堀りできる一人称視点の強みを殺してしまいますよ。
小説の一人称視点&三人称視点の書き方まとめ
- 小説における人称とは、『語り部が誰か?』ということ。
- 小説における視点とは、『どのように見聞きしているか?』ということ。
- 小説の一人称視点
- 物語の語り部は、主人公。描写できる情報は、主人公の五感で得られるものに限られる。主人公の内面を描写できるので、人物設定を深堀りしやすい。コメディ系の物語に適している。
- 主人公が知り得ないことを描写しないように注意すること。
- 小説の三人称単視点
- 特定の人物に的を絞り、まるで背後霊のように付き従って、物語を描写していく。付き従う相手のみ、内面を描写可能。
- 付き従う対象以外の内面を描かないように注意すること。
- 小説の三人称多視点
- さまざまな登場人物を通して、物語を描写できる。特定の人物に縛られることなく、視点移動が可能。客観的な情報に基づく描写しか出来ないので、登場人物の内面までは描けない。
- 小説の三人称神視点
- 全知全能の神の視点。あらゆる場所へ視点移動できて、全ての登場人物の内面も描くことが出来る。また、目に見えずに存在する物や過去・未来の出来事にまで言及できる。
- 小説の一人称視点&三人称視点のタブー
- 視点移動のやりすぎ
- 異なる人称視点を混ぜる
- 多くの登場人物で一人称視点は使う
